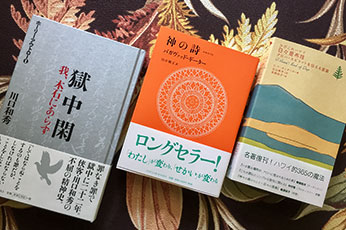MAGAZINEマガジン
青山堂運歩 by 川島陽一
形なき形・声なき声
表題の形なき形・声なき声とは実のところ「前彎調律」(以下、調律と表記します)へと至る現実(リアリティ)の説明なのです。
「調律」を体験された方々の声に耳を傾けると、「骨がポキンポキンと音がした」「からだの中をゴーッという音が鳴りました」「「下半身のゾーッとするような感じ」「首のあたりのポキンポキンという音がしました」などのお話をされることがあります。言葉を超えた感覚の次元とでもいいましょうか、通常の感覚知覚の表現でないことは明らかです。
超感覚的な諸々の次元で体験されたからだの存在感と現実感(リアリティ)は、多層構造を帯びて自己の真の存在を描きだすのだと思います。以下、東洋の智慧の究極を求めて、道家思想の哲学的かつ神秘的著作とみなされかつ最も重要であり根本的なテクストのひとつ『道徳経』(『老子道徳経』)を読みこの書に潜む人間の息づかい、脈打つ哲学者の精神を見てみましょう。そしてそのことが「調律」に伏在する、と思われる神秘の扉の鍵になりますことを願いつつ。
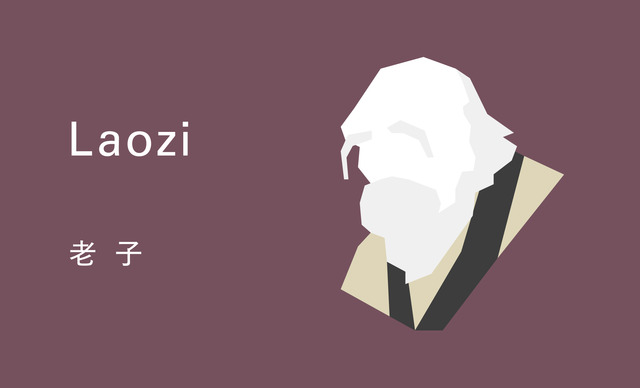
老子が書いたとみなされている『道徳経』。
老子の存在には諸説ありますが、そのことは他に譲り、『道徳経』という書物は実在する以上そして多くの著者が論考していることを踏まえて、以下いくつかの考えを述べたいと思います。まず『道徳経』という書物の中に、固有名詞が一度たりとも見えないことです。それは特筆に値するということを、老子研究でも有名な福永光司、井筒俊彦両氏のおっしゃるところでもあります。確かに、一つの人名も一つの地名も見当たらないのです。時間というものを歴史の時系列と考え、空間を風土として見ると、例えば『論語』は孔子の言行についての文脈の中において孔子自身はもちろん、その弟子、知人、王侯、大臣たちといった実在の人物たちに満ちあふれ、鮮明に生き生きと描かれています。
『荘子』は『道徳経』に並ぶ道家哲学の代表作でありますが、多くは神話形成的な想像の産物であり、その中には神話の想像的な人物が多く登場いたします。荘子は『荘子』の中において、弁証家の恵子や弁論家の公孫龍といった実在する人物に言及しています。老子もまた己を取り巻く個の人間や己と交渉をもつ具体的な人間、さらに己の生活している空間としての風土や村々に対して、切実な関心をもたないわけではありません。しかしながら、老子にとって最も本質的な関心は、それらの個別的、具体的、歴史的、風土的な特殊性ではなく、一切の存在の根源にあるもの、つまりは、永遠的普遍的なる「道」の真理にあったのです。形をもち、名をもつ森羅万象の世界よりそれらの根源にある、形をもたず、名をもたない「道」の世界こそ、第一義的な関心事であったのだとおもいます。
老子が関心を持っているものは概念であり、空間や時の制限を超えた永遠の観念でありますし、実在する人や物や場所、それらの現象的な名や形の背後、さらにはその彼方に存在する、何か、なのです。『老子』(朝日選書・福永光司)p515 解説の中で福永は「『老子』の中で固有名詞が全く見えない、という事実を、我々はどのように理解すべきであろうか。」と問います。井筒俊彦もまた、『老子道徳経』(井筒俊彦英文翻訳コレクション・古勝隆一訳、慶應義塾大学出版会)序 老子と『道徳経』三 p10 において「これとの関連において、『道徳経』一書全体を通じて、固有名詞がただのひとつも見当たらないことを、忘れてはならない。一つの人名も一つの地名も、である。古代中国には歴史的人物や具体的に実在した場所の名前に言及しない書物は事実上ないことから、これは非常に重要である。」、と言及しておられます。
我(イネイト・インテリジェンス)が、道(ユニヴァーサル・インテリジェンス)を観、道(ユニヴァーサル・インテリジェンス)が我(イネイト・インテリジェンス)を観る。我も道もともに名をもたない。名を超えたところで互いに向かい合っているところでは、己の名、つまり固有名詞は、全く必要のないものであり、無用のものでしかありえないでありましょう。「調律」のたどりついたところは、いじょうのような場所であったのです。
名の本質はあくまで他と区別することである。他と区別、差別されなければならないところに名の普遍的性格がある。しかし、己が直截的に道の前に立ちうる、「個」は直截的に「普遍」と結びつくところに「調律」の意義があるのだと思う。
イエスを媒介者として神の国へと入るキリスト教あるいは阿弥陀仏に導かれて極楽往生を願う浄土教などからひたすら離れた世界、(『神を超えよ!仏を超えよ!』積哲夫TAO LAB BOOKS)、がそこに存在していると言えないでしょうか。
固有名詞というものを、人間に限定して考えた場合、例えばキリスト教であれば、真理を体現するもの、それはイエスであり、イスラーム教であればマホメット、仏教であれば仏陀となる。真理は真理それ自体としてよりも、真理を体現する具体的な人格が需要であり、その人格への尊崇と帰依、一心なる信仰が決定的なものとなる。老子には道に目覚めた「己れ」が存在するのみである。道に目覚めた「己れ」という「個」(イネイト・インテリジェンス)が直截的に「普遍」(ユニヴァーサル・インテリジェンス)と結びつくところが、老子の根本的思考といえるのではないでしょうか。
道に関して老子は唐突に語り始める。絶対者、つまり道とは何か、道のヴィジョンとは何か、と。
老子はさりげなく、道がもつ否定的属性に言及する、道には「名がない」(「道常無名」『道徳経』第三二章)、と。さらに、「一本の条の如くに果てしなく続き、いかなる名も与えられない」(「縄縄不可名」『道徳経』第一四章)。「道は隠れてあり、名がない」(「道隠無名」『道徳経』第四一章)。
だが私たちは、荘子が次のように、老子の前史とでもいうべき方法で語ることを忘れてはなりません。「知の究極の限界は何か。始めからものなど存在していなかったのだとの見解が述べる段階がそれだ。これこそが知の極限であって、何もそれに付け加えることができない。」其知有所至香矣。悪乎至。有以為未始有物者、至矣、不可以加矣。(『荘子』斉物論篇第二、七四頁)
「だから、知の最高度の位とは、推論によってはこれ以上は知ることのできないという限界のところで動かぬままとどまることだ。言葉でない、言葉として現われることのできない言葉を知る人がいようか。道として捉えられない道を知るものがあるのだろうか。もしこのような者が存在するのであれば、その境地は天の自然の宝庫と呼ぶにふさわしい。在る(Being)という無限の宝庫の鍵をもつひとだ。そこではいくら注ぎ込んでも満ちあふれる恐れなどなく、いくら汲み取っても涸れることがない。これらの無限のものが、どこから湧き出るのか、その源を知るよしもない。その様な人の境地とは、苞光(ほうこう)(包まれた光、いぶし銀の光)と呼ばれるにふさわしい。故知止其所不知、至矣。執知不言之辨。不道之道。若有能知、此之謂天有。注為而不竭、而不知其所由来、此之謂葆光(『荘子』斉物論篇第二、八三頁)
ただひたすら、人為をやめた「自然のまま(イネイト・インテリジェンス)にまかせること(D・D・パーマー)」そのときにこそ、無限の美徳(ユニヴァーサル・インテリジェンス)が生まれ出る源に帰り行くのでありましょう。「道」や究極の絶対者はありとあらゆる概念や推論を超脱している。荘子を経ることでわたしたちは再び老子の「道」の哲学に帰還することになる。本来の性質の上に立ち、知れらず知ることのできないもの、それは「道」(ユニヴァーサル・インテリジェンス)。
道常無名。樸・・・始制有名。(『道徳経』第三二章)絶対的なリアリティとしての「道」には「名」がまるでない。その「道」は細工が加えられていない原木(樸(あらき))に喩えられる。・・・原木は、彫塑されて始めて「名」が存在する。「道」(ユニヴァーサル・インテリジェンス)、原木(我々の身体)=「名」(イネイト・インテリジェンス)という読み替えを通して、「調律」のリアリティ、その哲学の神秘のひそやかな兆しに、そこから万物が迸りでるのを、声で表現してくださいました多くのクライアント様に感謝を込めて本稿を終えます。