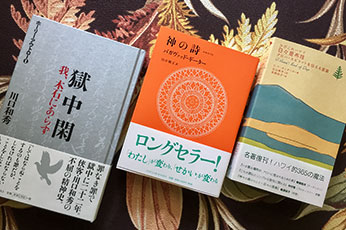MAGAZINEマガジン
青山堂運歩 by 川島陽一
色彩の排除(調律における)の哲学

色彩の領域(The Realns of Colour)を考えてみます。
東洋医学は江戸時代日本で漢方医学として広まりました。その医学を初めとして、絵画、詩歌、演劇、舞踊、茶道、生け花、剣に代表されます武道、どの領域においてであれ、色彩の領域に対する否定的な態度は、中国や日本の文化には、黒と白を除いたすべての色彩を排除するような、色彩の抑制及び抑圧へきわめて明らかな傾向が見られます。黒や白でさえも、色彩として機能することを止めますし、別の性質をもつものとして機能することになるのです。
中国や日本の水墨画は、色彩の抑制及び抑圧への最良の例として魅力のあるものといえます。独自の美意識の問題が深いところに存在します黒と白の否定、それをモノクロの世界と認識しますとその内には、「自然(イネイトインテリジェンス)」が生み出す汲めど尽きせぬ豊潤で複雑な形態と色彩が、黒い輪郭の極端に単純化された構図に導き出されます。そして、時には水でかすんで灰色に薄められ、時に輝くような黒色が点在するほんのわずかなひとふで、薄い黒色のひと塗りでコンストラクションされ、さらに背景はぼんやりとした灰色の入りまじった空間となります。背景の観察をするならば、ぼんやりとした灰色は、さらにおおかたの場合空白ないし白い空間から構成されるところの、筆の入っていない生(き)のまゝの絹ないし紙なのでした。
以上のモノクロの世界を、その美意識をさらに探求してまいりましょう。

五・七・五音節の三つの連続する単位に配置される十七音節で構成される、俳句と呼ばれる、世界の詩的表現の中でも最も控えめな形式、それは人をして禁欲的な芸術と呼ばれておりますし、やまとことばの思考展開の内なる特殊性、特異性とは何かと考えますと、俳句に先行します和歌こそは日本的同一性を創造的に志向し、外来語この場合漢語の他者的あるいは外来的な思考・思想の同化融合を同時並行的かつ方法論・自覚的に、日本的と言ってもよいほどに思想構造化してきましたし、組織的構造構成の軸を確立してきたといえます。
さらに色彩の排除の観点から見た場合、無常観の仏教的生老病死の観念の影響もですが、それよりも日本人が長い間に愛唱してやまなかったこの世における人の命のはかなさに対する歎きの心情、それは、みずからの身体(カラ)の内部に魂(タマ)を繋ぎとどめておくことの難しさの心持ちが重要な役割を演じてきたのでした。身体とは、魂(タマ)の単なる入れ物に過ぎないということなどは、まさに、色彩の全き排除の思想でもありました。
蝉が幼虫から成虫へと変身するさい抜け殻が残されるように、人間の身体からタマが抜け出してしまえば、あとに残るものは生命のないナキガラです。稲や栗のカラも、同じように、食べられる中身がなかったり抜け落ちたりする場合の殻粒であります。貝ガラも、食べられる中身を包んでいる外皮のことであります。とすれば、カラとは本来、充実した中身を覆い包むものを示す、と考えられましょう。ミ、とは、まさにカラに包まれた状態の中で満たされているものであると言えるでしょう。だからこそ、人が食物として摂取できる部分はミ(身・実)であり、わたしたち日本人は古来、自分のミになるような食べ物をミ、と呼んできました。
自らのミと外在するミとをどちらもミとするという考えは、ミの色彩の排除という思考から導き出されるところの、身体論、身心論とでもいえるのではないでしょうか。ひとのからだと外在する食物とが決して別のものではなかった。ひとのからだの肉の部分をシシと言いますが、ひとにとっての主なる食獣であった、縄文時代からのシシ(猪(いのしし)、鹿(かのしし)、カモシカ(カノシシ))との整合性も見逃してはなりません。
古代日本人がむずからのからだの内側にひそやかに感じとっていました、始原の身体感覚をさらに明らかにしようと思います。
「尋常(よのつね)ならずすぐれたる徳のありて、可畏(かしこ)き者を迦微(かみ)とは云うなり」
と本居宣長は『古事記伝』に記した。おそらく日本人は、そのように際立った感受性を太古の昔から「自然」がもつ色彩豊かで絵画的な姿、気象条件や一年の変転する季節、変化し続ける色彩と色合い、無限に変化しつづける目も眩むような絢爛たる錦に匹敵する感性を持ち続けてきたことから導き出されたのではないでしょうか。しかし、他方、その色彩の輝きの中に、慎み深さ、静かな地味さなど、「寡黙さ」が霞のように細やかに色彩を覆って外面的な絢爛さを緩和していたことも想像されます。
日本人の色彩感覚のきわだつ特性が発揮された時代の美的文化を見るために平安時代(七九四〜一一八五)(字義は「平和と安定」)の色彩溢れる、優雅さ、精巧さを見てみましょう。『源氏物語』に代表される宮仕えの女官たちによる作り物語や日記、随筆は、さまざまな色の名称に言及してい、その数は一七〇種以上にもなります。
「黄色い(イエロー)薔薇(ローズ)」とも呼ばれる「山吹」は天然色を連想させる輝くような黄色です。しかし、「花盛りの黄色い薔薇」を意味する「花山吹」は、外側の重ねが薄い落葉色、内側の重ねが輝くような黄色の組み合わせによって作り出される混合色で「夕暮れの黄色い薔薇」を意味する「夕山吹」とも呼ばれます。さらに「山吹匂(やまぶきにおい)」を見てみましょう。「山吹の香り」という意味の、当時の宮仕えの女官の衣装に用いられた標準的な重ね色目でした。最上部の輝くような黄色の重ねの内側に、何層もの重ねがあり、内側にいくにしたがって、徐々に薄い黄色になり、最後には、深い紺色の重ねになるのです。
矢代幸雄(一八九〇〜一九七五)は、『日本美術の特質』(岩波書店)の中で日本美術に関して「印象性」、「装飾性」、「象徴性」、「感傷性」という四つの特徴を挙げておられます。その中で日本美術に表現される精神的内容、そこに反映される日本人の精神的性格の特徴は「感傷性」だと述べています。さらに日本人は自国の気象条件やその「自然」が持つ色彩豊かで絵画的な姿のおかげで、太古の昔から、一年の変転する季節とともに、変化しつづける色彩と色合いに対する際立った感受性を発達させた、といいます。 日本の「自然」は、無限に変化する色彩をもつ絢爛たる錦に匹敵している、とも。
平安時代は、このように、「色彩豊かな」時代でありました。しかしながら、平安貴族の美的感覚がかもしだす煌びやかで色彩豊かな世界のただなかでさえ、ある種の落ち着き、静寂を認めることもできるのでした。多くは色が上品に抑制された穏やかな色なのです。この古代の時期に色彩の抑制への傾向が確認できるかと思います。実際には平安貴族の目には「黒」は、冴えない陰鬱で不快な更には不吉な色でもありました。「黒」は彼らには死を思い起こさせる、世俗の快楽を捨て出家することを連想させるものでありましたでしょう。
にもかかわらず、『源氏物語』の作者、紫式部には、黒に最深層の美を見いだすことが出来る審美眼がありました。暗く色彩のない世界、それは実のところ、至高の美へとむかう、もののあはれ、であったところにわたしたちは驚かされもします。
日本人は次に、謹厳で形も色彩もない深淵なる本質の世界を悟ることになります。その時代は、禅仏教の悟りの世界が広汎に隆盛しますところの鎌倉時代(一一九二〜一三三三)でした。第一級の画家たちは、禁欲的で抑制された精神に由来する、水墨画の傑作を生み出します。その画僧らは、「室町時代(一三九二〜一五七二)に、水墨画を、見るものの心のなかに抗い難い憧憬を掻き立てました。
そして、わたしたちは、溢れんばかりの色彩と豪華な装飾の趣向の桃山時代(一五七三〜一六二五)を向えます。日本の歴史の中で、これほどまでに色彩と意匠が惜しみなく大胆に発揮された時代は、かつてありませんでした。平安貴族の絢爛な優美さは、ともすると柔弱さへと傾きましたけれど、武士の時代であった桃山時代は逞しさ力強さに満ちあふれておりました。
絵師たちの筆頭にいました、狩野永徳(一五四二〜一五九〇)は、大胆な筆遣い、雄大な意匠、鮮やかな色彩による装飾を用い、いわゆる桃山様式を体現する画家でした。注意すべき極めて重要なポイントとしては、このような色彩が豪華絢爛に誇示されるその裏には、力強い水墨画という、全く別の世界が存在していたということでありましょう。
つまり、桃山時代は、色彩の排除という水墨画の趣向に裏付けされた、色彩の誇示の趣向を特徴とします時代でありました。そこへの示唆を与えますのは、茶道という、独自の技法でありました。茶聖利休(一五二二〜一五九二)は、侘茶、侘びの茶を意味します独自の技法を完成させました。「侘び」は、日本の最も根本的な美的カテゴリーのひとつ。定義するならば、寂しさ、貧しさ、簡素さに集約されましょう。色彩の排除に裏打ちされます無色の状態、「色を抑える」ことが、色彩の微かなる面影を感じさせることになるのでした。
色彩の不在という色彩の消極的なありかた、という存在性のパラドキシカルさを、茶人たちの座右の銘としてたびたび引用せれる和歌を見てみましょう、
見渡せば 花も紅葉も なかりけり
浦の苫屋の 秋の夕暮れ
藤原定家卿(一一六二〜一二四一)が詠んだ和歌が、「調律」を現していることに、気づいていただけたならば幸いです。浜に佇む漁師の苫屋に象徴される無色の色彩の次元において、晩秋の侘びしい原野は、色彩を絶対的「空」の次元へと還元されるのです。