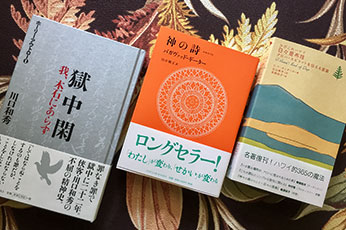MAGAZINEマガジン
青山堂運歩 by 川島陽一
「音(シニフィアン)」と「意味(シニフィエ)」
フロイトやユングの深層心理学における言語論を別として、西洋の言語学の圧倒的大勢は言語に対して言葉の社会的記号コードとしての側面、発話行為を含めて水平的(ホリゾンタル)なアプローチとなるのが一般的だ。人間の言語意識において、深みに向かって掘り下げていく、垂直的(ヴァーティカル)なアプローチは完全に無視されるのが現状である。
言葉が「意味」を通じてこの世界を生み出すということ、つまり、言語的「意味」の存在喚起機能を、人間の深層意識にまで垂直に降りていき、そこに働く「意味」の生成エネルギーの現場をとらえていかなければならない、と思うのである。
浮遊状態のアミーバのごとくに伸び縮みする意味エネルギー、『周易』(易経)の記号体系は、陰陽二気の「八卦(はっけ)」の展開過程において、大宇宙の森羅万象を、八つの元型的な深層的意味形象に還元しようとする。
「乾(けん)」「坤(こん)」「震(しん)」「巽(そん)」「坎(かん)」「離(り)」「艮(ごん)」「兌(だ)」
「乾」は天、「坤」は地、「震」は雷、「巽」は風、「坎」は水、「離」は火、「艮」は山、「兌」は沢に当たるとされているが、これら「八卦」の意味する天や地、その他の自然物は、私たちの常識の考える自然物ではない。それぞれの陰と陽の三爻(こう)の組み合わせからなる記号の姿や形が、私たちの意識の深層領域に呼び起される遊動的で浮動的な意味エネルギーが、なにがしかの、ゆるみ、を含んだ方向に向かって凝集していこうとするものなのである。
『易』の形而上学の垂直的なアプローチは、言葉よりもむしろ陰陽の気のエネルギーを考える。ユダヤ教神秘主義カッバーラーでは「数(セフィーロート)」を神聖視しそれを宇宙的存在喚起エネルギーと見る。人格的創造主としての神を宇宙の始原に表わし、それの創造的意志を存在喚起エネルギーと考える人もあろう。宇宙的大生命、全宇宙にみなぎる悠久の生命の流れについて語る人々、ルドルフ・シュタイナー、カール・ユング、D・D・パーマーなどなど。根源的感覚は同一であっても、それを具体的に表象し、理論化する仕方は様々である。
老荘思想に目を転じてみよう。『荘子』の「天籟(てんらい)」の比喩である。『荘子』内篇第二(斉物(せいぶつ)論篇)、斉物論とは、「物を斉(ひと)しくするの論」という意味であり、万物斉同、絶対無差別の論理が展開される。
楚(そ)(古代中国紀元前11世紀~前223年)の隠者、南郭子綦(なんかくしき)とその弟子顔成子游(がんせいしゆう)との対話である。
子游曰わく「地籟(ちらい)は則(すなわ)ち衆竅(しゅうきょう)是れ已(のみ)。人籟(じんらい)は則ち比竹是れ已。敢(あえ)て天籟を問う」と。
子綦曰わく「夫(そ)れ万(よろず)の不同を吹きて、其れをして巳よりせしむ。咸(みな)、其れ自ら取れるなり。怒る者は、其れ誰(たれ)ぞや」と。
子游がいった。「お教えにより、地籟とは無数の洞穴がたてる音のことであり、人籟とは笛などの楽器の音であることを知りました。それでは天籟とは何か、お尋ねしたいと思います」
すると、子綦綦は答えた。
「それはほかでもない。さまざまの異なったものを吹いて、それぞれに特有の音を自己の内から起こさせるもの、それが天籟である。万物が発するさまざまな音は、万物がみずから選び取ったものにほかならない。とするならば、真の怒号の声を発しているのは、はたしてなにものだということになるのであろうか」
荘子はさらに思索の別のアプローチ、絶対者が「一つ」である、「対立物の一致」としての「一」なのだ、と言う。「道」、それは絶対者。それは、天の等化作用。つまり、「天鉤(てんきん)」という形而上の状態、あらゆる対立と矛盾を、等しくする絶対的「一」。
天下莫大於秋豪之末、而大山為小、莫寿乎殤子、而影祖為夭。天地与我並生、而万物与我為一。(『荘子』斉物論篇第二、七九頁)
「天欽」、天の等化作用から見れば、最小が最大であり、瞬間は永遠である。ありとあらゆるものは時空双方に関して一単位となる。しかし、荘子は、精緻な推論を展開したのちに、直観的絶対的な、知、に対して忘我状態のままに留まれ、と忠言する。この結論こそが、老荘思想の出発点となる。
道沖而用之或不盈。(『道徳経』第四章)
「道」はからっぽの器だ。幾ら使おうと、それを一杯にすることは決してできない。
大盈若冲、其用不窮。(『道徳経』第四五章)
大いなる充満はからっぽに見える。だが(実に、それが充満してあるのは)実際に使ってみれば、決して使い尽くせない(ことからわかる)。
意味生成のエネルギーの現場、それを老子は、『道徳経』第一章、第六章、第六一章、で語る。
無名天地之始。有名万物之母。(第一章)
名を欠くこと「無名」こそが天地の始まり。名づけられて在るもの「有名」こそは。万物の母。
玄之又玄、衆妙之門。(第一章)
それは実に、神秘のなかの神秘。そしてそれは、無数の不思議が出て来る門。
牝常以静勝牝、以静為下。(第六一章)
牝は常に、静かなことで牝に勝つ。静かであることで、常に、より低きを占める(より低きを占めることで、牝は結局、より高きを獲得する)。
「道」が帯びる無限の創造性は、「門」で象徴される。「牝」の動物のイマージュは、その象徴の働きとして、多産なること、母なることを思い起こさせよう。「牝」が、かよわき者の弱さだけでなく、老子に特有の、逆説的な、かよわさ、卑(ひく)さ、脆(あやう)さ、静かさは、逆に、無限に強く、剛強で、高きに存在することをいう。
「意味」生成のエネルギーの現場のお話はここまでにして、ここからは、またリモート(遠隔)の話しである。シニフィエ=意味を働かせる、シニフィアン=「音」、の話である。音を深みに向けていく行為が、リモート(遠隔)。音がいかに大切か、いかに大事か、ということ。人の深層意識の底の底まで、音を発していくこと、に尽きるのである。ホリゾンタルでなく、ヴァーティカルに、である。
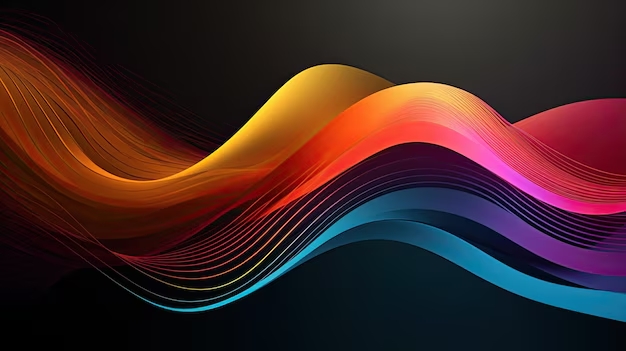
「道」というからっぽの器にそしてその創造性の「門」に、あなたは、あなたの発する「音」は、はたして、どれほど一杯にできるのだろうか。