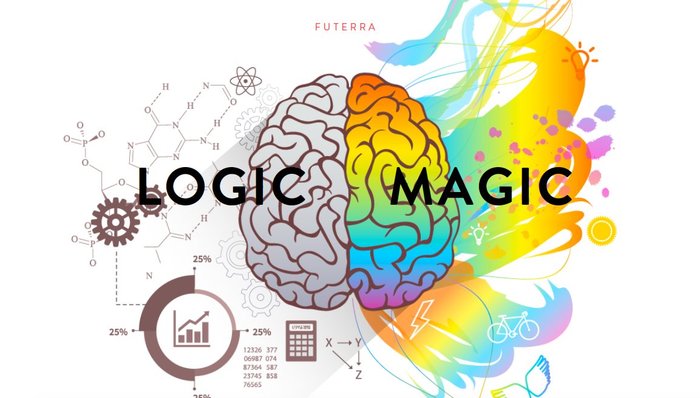MAGAZINEマガジン
青山堂運歩 by 川島陽一
調律・調整の真の構造―呪術(マジック)と論理(ロジック)をめぐってー
ここ数回に渡り、リモート(遠隔)の構造を書いてきました。「即身成仏と空海」「時々刻々その2」など、です。
いつも、難しいと、皆さまからおしかりを受けております。誠に、申し訳のないことと思っております。何をお伝えしたいかと言いますと、多くの方から、お礼はどうなのか、と言われていて、私は、凡人ゆえ、ときどき、まぁ〜お布施を頂けたらなあ、などのたわごとをうっかり言ってしまう日々なのです。
ですが、これは、何より、道元さんによりかかりまして、一切のお金に関わることを発生させない、と心に誓うのです。見返りは、何なのか、と言いますと、あの「魔法の言葉」を頂くことに尽きるのです。それは、お礼の言葉、なのです。かぎりない、至福のときを、その時、私は迎えるのです。
論理的に言えば、整体でお金を頂戴していることと、リモート(遠隔)でもお金を発生させることを、同義、ととらえることは、確かに、論理にかなっている、でしょう。しかしながら、リモート(遠隔)の行いを、「呪術(マジック)」ととらえた場合に生じる主題の難解さと不確かさを考えてみますと、ことはそう簡単ではありません。「呪術」や「呪術的なもの」という観念自体は、実際、表面的にはきわめて単純明快のように思われます。しかし、言語活動の「意味」そのものに潜んでいる、呪術的側面を解明するという行為自体、さらに、その言語呪術のすべての隠れた源泉へと降りていくとき、深刻な困難が現われるのだと思います。
子どもが初歩的な言葉で獲得するのは、言葉という的確な身振りをとおして世界という事物へと、その力を行使することです。わたしたちの誰でもが、幼児期や子ども時代に名づけという驚くべき呪術を行使することが出来る。要するに、言語によって周囲に命令することが出来ることを子どもは理解するのです。もし幼児が例えば「ママ!」と叫べば、その言葉はそこに母親がいることを記述しているのではなしに、彼女からのある行為を要求するのです。そして、その機能は決まっていて、それは命令機能なのです。
ゲーテの『ファウスト』では、言語呪術の源泉を想わせる一節がある。
戦慄が穹窿(まるてんじょう)の暗がりから吹き下りて
さあ、われに触れよ
われは気づいている、わがまわりを汝の漂うを、
呼び寄せられし精霊よその身を現せ
(ゲーテ『ファウスト』第一部「夜」)
文学作品ではあるものの、魔法の呪術的プロセスなのであり、「意味」の潜みを現していると言えましょうか。あらゆる言葉は、象徴としての本姓をわたしたちの心に、何かを呼び起こすに違いありません。
道元に戻りましょう。
真の自己(我)を、その根源性において捉えることが禅である。「直指人心、見性成仏」とは、真の自己の覚知を意味する。
『信心銘(しんじんめい)』(禅第三祖僧璨(そうさん)の著作)の一節に
「能は境に随って滅し、境は能を逐って沈む。境は能に由って境たり、能は境に由って能たり。両段を知らんと欲せば、元是一空。一空、両に同じ、斉しく万象を含む」
とある。その意味は
「主体(能)は客体(境)がなくなるとともになくなり、客体の方も主体が消滅すればそれにつれて消え去る。主体があるからこそ、それに対して客体は客体なのであり、反対に客体があるからこそ、それに対して主体は主体として定立されるのである」
と主・客の縁起性を説く。
続く後半は
「今、私は主・客(能・境)を二項対立的な形で語ったが、これらの二項が本来何であるのか、と究めてみれば、両者は(縁起的にのみ、すなわち相互の純関係性においてのみ存立するという意味で)もともと同一つの空ではあるけれども、(つまり、それ自体としてはなんらの実体的差別性をもってはいないけれども)、しかもまた同時に、(それ自体に本具する縁起的機能を通じて、非実体的差別性を現成し、主・客二項に自己分岐する。この意味で)一空は、互いに対立するところのこれら二項と自体的に完全に同定されるのであって、従ってまた、ありとあらゆる事物事象が、例外なく、本有的に含まれてとも言いうるのである」
と主客間の著しくダイナミックな可塑性を示唆している。
(参考:『コスモスとアンチコスモス』 Ⅴ禅意識のフィールド構造P389~390、井筒俊彦著、岩波文庫)
「空」、「無」を大乗仏教哲学の伝統にのっとって、「心」、「心性」、「心法」あるいは、「自己」として、主体性の在り処を禅は考えるのであり、臨済はそれを「人(にん)」とも表現する。
真の自己の覚知とは、自己という主体が、普通の意味での主体であることをやめなければならない。そうしなければ、物の真相はけっして現われてこない。どうすればよいのか。主体の立場を、同一平面(ホリゾンタル)上に移すことでなしに、垂直(バーティカル)に転じさせなければならない。
「空」→「主・客」→「世界」、を全体領域として成立させるのだ。
臨済がこう言う
「道流、錯(あやま)ることなかれ。世出世の諸法は、皆自性なく、亦た生性(しょうしょう)無し。但だ空名有るのみにして、名字も亦た空なり。伱(なんじ)祇麼(しも)に他の閑名(かんみょう)を認めて実と為す。大いに錯まり了れり」
(君たち、皆間違ってはいけない。世間も出世間もひっくるめて一切の存在者は、本質もないし、またそれの現象形態も本物ではない。ところが君たちは、そんな空虚な名前をありがたがって実だと思っている。)
言葉によって支配される「主・客」対立の世界にある一切の事や物は全て「無」=「空」であり、ただある、と思われるものは「空」名のみ、と『信心銘』もいう。
「唯有空名。幻花空花。不労把捉」
(「幻花空花、把捉を労せず」)。
『金剛経』「応無所住而生其心(おうもしょじゅうにしょうごしん)」のサンスクリット原文をみてみよう。
Evam apratisthitam cittam utpadayitavyam
Yan-na kvacit-pratisthitam cittam utpadayitavyam
(かくのごとく、固着せぬ心が起こされるべきである。何かに固着したような心は一切起こされるべきではない)と表わされている。つまり「応無所住・・・・・」とは存在の無分節性の自由を保ちながら、しかも存在の分節態に縛られないように、心を働かせていくべきである、ということ。
これが、「無心」の本来のあり方である、ということを『坐禅箴(ざぜんしん)』(宏智正覚(わんししょうがく))は次のように描写する。
「・・・・事に触れずして知り(自分の外に客観的な象を見ることなくして認識し)、縁に対せずしてして照らす(外境に対立することなくして、しかも了了と存在界を証明する)。事に触れずして知る、その知おのずから微なり。縁に対せずして照らす、その照おのずから妙なり。その知おのずから微、曽て分別(差別)の思なし。その照おのずから妙、曽て毫忽(ごうこつ)の兆しなし。曽て分別の思なし。その知、偶なくして奇なり(対立するものはない)。曽て毫忽の兆しなし、その照、取なくして了す。水清くして底に微す、魚行いて遅遅たり。空闊(ひろ)くして涯(かぎり)なし、鳥飛んで杳杳たり。」
リモート(遠隔)のおこないは、じつは、むつかしいことではないのですけれど、あえて方法はお伝えもしませんし、お教えすることもないのです。師とぼくが勝手に思っている空海さんは、「この法を安易につたえてはならぬ」と言っているからです。ですが、古代日本人が「迦微(カミ)」と言いましたときにさかのぼり、文字なき世にはおのずから世世伝えられていた、人を想う心を伝える、ということを心しているだけであります。
いつもまとまりのない文章ですが、御拝読感謝申し上げます。