MAGAZINEマガジン
平凡な覚醒 by しろかげ。
ガラスの繭 プロローグ
体の起伏に添って3D成型されたガラスの棺は、まるで透明な繭のようだった。
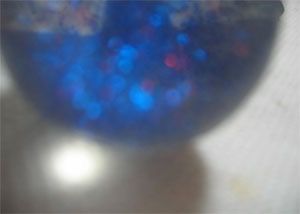
棺を満たしている溶液は夜が白む5分前の空のような色をしており、その中に浮かぶ枯れ木のような肢体が、ちらと揺れたように見えた。白衣の技師たちが二人、打ち合わせ通りといった体でシーリングを点検し終えると、棺を載せたアームが水平にスワイプして、繭は壁の装置へ飲まれて行く。
母は遅れて到着した私に気づくと、新鮮なうちにレンダリングへ回さないとお父さんの思い出をキャプチャー出来ないんだよ、と短く説明して待ち合いの椅子に腰をおろした。こんな場面で新鮮という言葉を夫の亡骸にあてがう母に、つうと生暖かい体液が私から溢れた。
「お父さん、透明になるまで2時間かかるそうだよ」
人体を透明化する技術は、平成の終わり頃から開発が進んだ。はじめ人々は透明人間の夢に期待を膨らませたが、そもそも細胞のタンパク質を固めて脂質を取り除くための薬液では生きた状態の組織をガラス化させるのは不可能で、ファンタジーが現実になることはなかった。研究は仕分け寸前に追いやられたが、量子コンピュータの出現が流れを変えた。その巨大な計算力は、丸ごとガラス化された亡骸からビッグデータを抽出解析し、生前の意識の動向をデータ保存可能にしたのだ。
この技術が人類の葬儀に革命を起こすのに時間はかからなかった。もちろん今でも多くは伝統的な火葬によって遺灰を墓に葬るのだが、ガラス化によるデータ埋葬が選択されることが今では一般的になってきている。
「色がだいぶ抜けてきたねぇ」
母の視線の先には、刻々と脱色が進むガラスの繭がモニターされている。ついさっきまで中が見えないほど深いドーンパープルだった溶液は、今や薄いピーチピンクにまで澄みあがって、硬質な皮膜の向こうには固まり切らないゼラチン様の物体が視認できる。ステータスバーは硬化率63%を示していたけれど、モニター越しの父はむしろ、強く揺すれば崩れてしまうような脆さに見えた。
「頑固な人だった」と呟いた母は、いつのどんな出来事を思い返しているのだろう。
「うん、冷徹だった」
石橋を叩いても渡らない父は、冒険的好奇心に駆られがちな私と反りが合うことはなく、私の生を圧倒的に制圧した。その君臨が今、輪郭だけを残して透明になって行く。
「きっと蒼いんじゃないかねぇ。お父さんの石」
「え?」
学生時代の終わりに家を出て以来、かつての私の部屋は父の書斎に模様替えされ、父は多くの時間をそこで過ごしていた。空の広い窓があって、月の夜は南の尾根がくっきりと陰影を極めて、そうだそう言えば、夜空が蒼く見える部屋だった。灯りを消して息を吸うと、胸の底まで染まりそうなくらいに。
2時間後、父は3カラットほどのガラスチップになって帰ってきた。凝縮された生の痕跡を、母は「立派な石だねぇ」と咽び泣いた。父の石は滑らかに歪んでゆらと光り、私の横隔膜を穏やかな温度に満たしながら散って行った。


